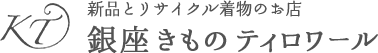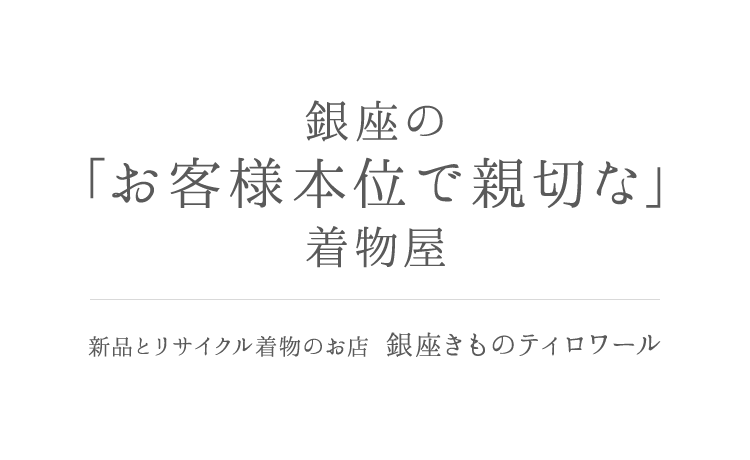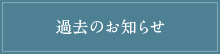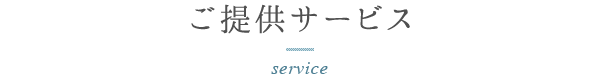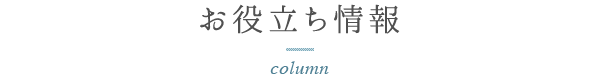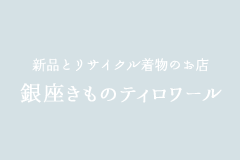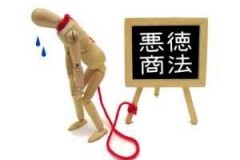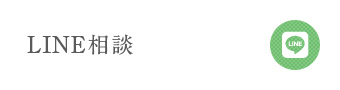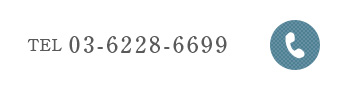-
2023.09.01 コラム 着物購入のポイントと注意点
着物購入のために知っておくこと当店で扱っている着物は新品とリサイクルがあります。さらに新品でも反物など生地から誂える場合と仕立て上り(プレタ)の2種類あります。どのような着物を希望するかが大事です...
-
2022.07.07 コラム 着物の種類と格
着物の格と種類と着て行く場所着物を着る時は、格を意識しなければいけません。着物、帯、小物全てに格があります。このことが着物を難しくして、着物離れを増やしていると言えます。しかし、格を意識した着方を...
-
2021.12.01 コラム 着物初心者にアドバイス!何を買ったら良いですか?
これから着物を着てみたいと思う方が男女問わず増えています。しかし、なかなか一歩踏み出せない方も多いようです。その理由としては、「何を買ったら良いか分からない」「どこで買ったら良いか分からない」「い...
-
2021.08.14 コラム プロが教える着物を買ってはいけないお店とダメな店員
着物を買ってはいけないお店の特徴とは?楽しい着物ライフか、後悔ばっかりの着物ライフかというのは、お店や担当者の影響が大きいですね。一番ダメなのは、欲しくもない着物を買わされたり、支払いが大変なのに...
-

取扱商品は、リサイクル着物・帯・羽織コートと新品着物・帯・小物です。銀座店での販売とともに、LINE・ZOOMを利用したオンライン販売も行っております。
-

リサイクル着物を中心に通信販売を行っております。店舗販売品と同様に丸洗い済みの状態が良い物のみご用意しております。
-

購入したリサイクル着物の着付けと着付けを覚えたい方は着付けレッスンがあります。
-
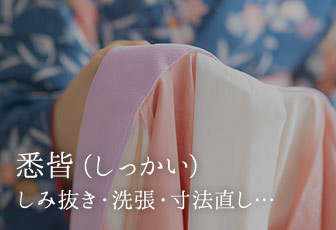
悉皆とは「しみ抜き」「洗張」「染替」「裏地の交換」「寸法直し」など着物の加工です。当店は悉皆が得意な着物屋です。お気軽にご相談ください。
-

店舗買取、出張買取、宅配買取に加え、着なくなったお着物や帯を委託販売いたします。
-

銀座店にて着物レンタルを行っております。実際の着物を見ながらお選び頂けます。
-
2023.12.13 浴衣について
高級な浴衣は、百貨店に行ったり、ネットショップを見て買う人が多いですよね。竺仙、三勝、有松絞りなどはブランドですから、安く売っている店はほとんど無いですね。なぜ、高級浴衣は安く売らないのか?それは...
-
2023.12.01 夏着物
紗袷せと無双と二重紗を同じ着物用に言っているお店や人がいらっしゃいますが、それぞれ別な着物です。ここでは、その違いと着る時期をお話ししますね。 紗袷せとは紗袷せは、絽や紗の生地の上に紗の記事が二重に...
-
2023.11.29 着物について
長襦袢の種類と着物との組合せとは?留袖と訪問着と紬に着る長襦袢はどんな色柄が良いのか、分からない方が多いと思います。初心者にとっては、長襦袢は下着なので、式服でも普段着でも同じで良いと思っている方...
-
2023.11.24 着物販売の法律
最近、このブログの法律関係や買ってはいけないシリーズが良く読まれています。1月、2月は展示会やらバーゲンセールやら売り出しが多いし、3月が年度末なので呉服屋さんもさらに力が入っています。普段からしつこ...
所在地
〒104-0061 東京都中央区銀座5-7-10 イグジットメルサ4階
営業時間
11:00~20:00